健康を守るカギは「糖と血流」そして自然な暮らし
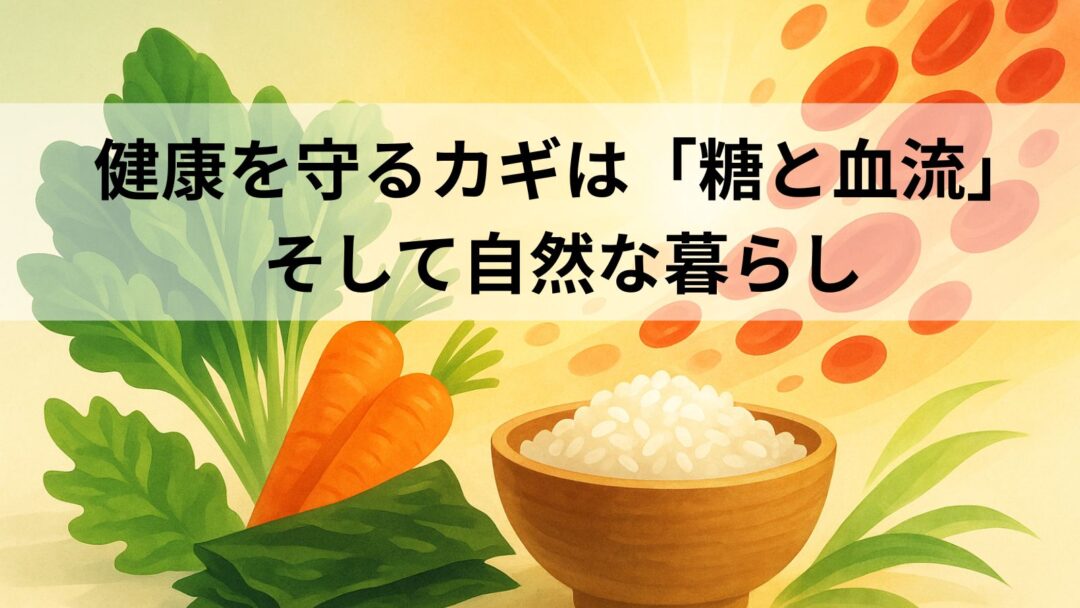
現代人の多くが抱える健康課題の背景には、「食生活の乱れ」と「栄養不足」があります。
コンビニや加工食品が手軽に利用できる一方で、私たちの体に本当に必要なミネラルや電子は不足しがちです。
血流を支える赤血球の働き、生命の基本エネルギーである糖の代謝、そして酸化と還元のバランス。
これらは一見難しいように思えますが、実は日々の食生活の選び方に深く関係しています。
本記事では、光合成から糖の代謝、血流を支える電位差、ゼータ電位の役割、さらにミネラル不足や油・水・食の問題までを幅広く取り上げ、自然な視点から健康を考えます。
最新の知見や伝統的な生活習慣を交えながら、病気予防と体質改善のヒントを見つけていきましょう。
糖とエネルギーの関係
生命活動の基本となるのは「糖」です。
植物は光合成によって水と二酸化炭素からブドウ糖を合成し、その糖をエネルギー源としています。私たち人間も同様に、糖を分解して体を動かすエネルギーを得ています。
糖は単なるエネルギー供給源にとどまらず、脂肪やたんぱく質の材料にもなります。例えば、糖は体内で脂肪に変換されやすく、余剰分は脂肪肝や動脈硬化の原因となります。
また、窒素や硫黄と結びつくことでアミノ酸が生まれ、たんぱく質合成にも利用されます。
しかし、糖の代謝がうまく働かないと健康に大きな影響を及ぼします。糖尿病はその代表例であり、近年では「マグネシウム不足」が深く関与しているとの指摘があります。
つまり、糖の代謝は糖そのものだけでなく、ミネラルの摂取状況にも左右されているのです。
救急医療の現場では「塩とブドウ糖」が基本の点滴として使われますが、これも糖がいかに生命維持に不可欠かを物語っています。
血流と電位差の秘密
私たちの体内を流れる血管の総延長は、なんと約10万kmにも及ぶといわれています。これは地球を2周半するほどの長さであり、血液はその全身ネットワークをわずか30秒で循環します。
心臓のポンプ機能が中心的な役割を果たしていますが、それだけでは到底このスピードを維持できません。
実は血流を支えるもう一つの力が「電位差」です。体内では電子のやり取りによる電気的エネルギーが働き、血液の循環を助けています。
古くは「気」や「チャクラ」といった言葉で表現されてきましたが、現代的に解釈すると「イオンの働き」や「電気的エネルギー」と言い換えることができます。
この電位差がスムーズであるほど血流は効率的に保たれ、酸素や栄養素が全身にいきわたります。逆に電位差が乱れると血液の流れは滞り、さまざまな循環障害を引き起こす要因となります。
つまり、血流は単なる物理的な流れではなく、電気的なエネルギーが関与する高度な仕組みで成り立っているのです。
赤血球とゼータ電位
血液の流れを決定づける重要な要素のひとつが、赤血球のまわりに存在する「ゼータ電位」です。
赤血球はその表面をマイナスの電子で覆われており、その外側をプラスの電位が包み込む二重構造をしています。
この仕組みによって赤血球同士は反発し合い、適度な距離を保ちながらスムーズに流れることができます。
この反発力こそが「ゼータ電位」であり、血液がサラサラでいられるかどうかを左右します。ゼータ電位が十分に保たれていれば、赤血球は互いに凝集することなく健康的な血流を実現します。
しかし、油や酸化した食品、過度な酸化ストレス、あるいは血球サイズや末梢血管の状態によってゼータ電位が低下すると、赤血球は凝集しやすくなり、血液はドロドロの状態へと傾きます。
その結果、循環不良や動脈硬化といった血流障害のリスクが高まるのです。
逆に、ゼータ電位を保つ生活習慣――新鮮な食材を選び、酸化ストレスを減らす工夫――は、血液環境を整え、健康寿命の延伸に直結します。
現代人に不足しているミネラル
現代の食生活において深刻なのは「ミネラル不足」です。特にコンビニや加工食品に頼った食事は、必要な栄養素の半分も満たせない場合があります。
例えば、成人に必要とされるカルシウムは1日550mgですが、コンビニ食中心ではおよそ125mgしか摂取できません。
同様に、マグネシウムも23.9mg必要なところ、実際には12.2mgしか取れていないといった具合です。鉄・亜鉛・銅といった必須ミネラルも軒並み不足しているのが現状です。
このように、カロリーは足りていても栄養バランスが崩壊している状態は「隠れ栄養失調」とも呼ばれ、数年以内に重大な病気を引き起こす可能性が高いと警告されています。
解決策のひとつとして注目されているのが「自然塩(特に焼塩)」の摂取です。精製塩ではなく、にがりを含む自然の海塩はマグネシウムや微量ミネラルを豊富に含み、現代人の不足を補ってくれます。
さらに、玄米や海藻、生野菜などを積極的に取り入れることで、体に必要な電子やミネラルを取り戻すことができます。
健康維持の基本は「食を元に戻すこと」。自然な食材から必要なミネラルを補うことが、病気を遠ざける第一歩となるのです。
油・水・食生活の見直し
健康を考えるうえで、私たちが日常的に口にする「油」と「水」は非常に大きな影響を持っています。
まず油について。人間より体温の高い動物の油を摂るのは不自然であり、抗生物質やホルモン剤を含んだ畜産由来の油は体に負担をかけるとされています。
私たちの祖先は、ごま油やえごま油など自然な植物性の油を中心に取り入れてきました。血管を守るためには、現代でも「サラサラと流れる油」を意識することが大切です。
次に水。水は高い場所から低い場所に流れる性質だけでなく、地下から地表へと湧き上がる力も持っています。
この自然な循環が、作物や生態系を支えてきました。しかし現代では、電子レンジで加熱した水や食べ物が「周波数を変化させる」という指摘もあり、体内の水に影響を及ぼす可能性が懸念されています。
さらに食生活全般に目を向けると、日本人の食文化の変化には戦後の政策的な影響もあり、肉や加工食品中心へと大きくシフトしました。その結果、現代病の温床となる要因が広がったと考えられます。
本来の健康的な暮らしを取り戻すには、自然な油や水を意識し、伝統的な食生活へ立ち返ることが求められます。
がんと生活習慣へのアプローチ
がんの発症や進行には、日々の生活習慣が深く関係しています。近年注目されているのは「免疫力を高めるシンプルな習慣」です。
その一つが「笑うこと」。顔の筋肉を動かすことで副交感神経が優位になり、免疫を担うNK細胞(ナチュラルキラー細胞)が活性化すると言われています。
また、体温を上げることも免疫力を高める基本であり、入浴や運動によって血流を促進することが推奨されています。
さらに、食生活の見直しも大切です。江戸や明治期の伝統的な和食に回帰することは、体を整える有効な方法とされています。
中には「三日食べなければ七割治る」といった断食の実践者もおり、現代でも定期的な断食や一日一食が体のリセットに有効とする説もあります。
また、近年では「サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)」の働きが注目されており、断食やカロリー制限がその活性化に関与すると考えられています。これは細胞の修復や老化抑制に関わるため、若さや健康を維持するための重要な鍵となります。
つまり、がんの予防や改善には、薬や治療だけでなく「笑い」「体温の維持」「伝統的な食生活」「断食」といった自然な生活習慣を取り戻すことが大切なのです。
まとめ
健康を守るために大切なのは、特別なことではなく「自然に沿った暮らし」を意識することです。糖や血流の仕組みを理解し、ゼータ電位を保つ食生活を心がけること。
さらに、不足しがちなミネラルを補い、自然な油と水を選ぶこと。
笑いや断食といったシンプルな習慣も、免疫力を高める有効な方法です。
現代の便利さに流されすぎず、伝統的な食と生活の知恵を見直すことこそが、病気を遠ざけ、心身を健やかに保つ鍵となります。
